
こんにちは管理栄養士の下山です。花粉のピークがやってきましたね。関根薬局でも花粉症のご相談も増えてきました。「なんだかいつもより症状が重い」「薬がなかなか効かなくなってきた」そんな方は、普段の生活習慣にも原因があるかも知れません。薬と合わせて普段の生活を見直しましょう。
今回は、その原因の一つに多い「水分補給」についてご紹介します。
水分補給は大事なことですが、誤った飲み方や自分の体質に合っていない量(不足・飲み過ぎ)によって体調を崩される方も多いです。冷たいものの飲み過ぎや一気飲みは胃腸に負担をかけたり、水分代謝(摂取した水分を汗や涙、鼻水などの体液に作り変え体内外を循環させること)がうまくできなくなってしまいます。
また、鼻水や鼻詰まり、くしゃみなど、花粉によるアレルギー性鼻炎の症状は、東洋医学では「水分代謝の異常=水毒」ととらえる考え方があります。水毒とは、体内での水の代謝や排泄が正常に行われていない状態のこと。余分な水が体内に蓄積し、鼻水となって出てきたり、鼻が詰まったように感じたり、めまいや頭痛などの症状にも繋がることがあります。
花粉症や後鼻漏などの鼻のトラブルが多い方、なんとなく春は体がだる重い・体調を崩しやすいという方は、意識してみてくださいね。

① 少量をゆっくり飲む
ひとくちずつ、ゆっくり飲むようにしましょう。健康のために白湯を飲んでいるという方も、1回に多量を飲んでしまうとかえって胃腸の負担となってしまいます。
ついつい一気にたくさん飲んでしまうという方は、コップの大きさを小さめのものにして飲み過ぎを防止するとよいでしょう。
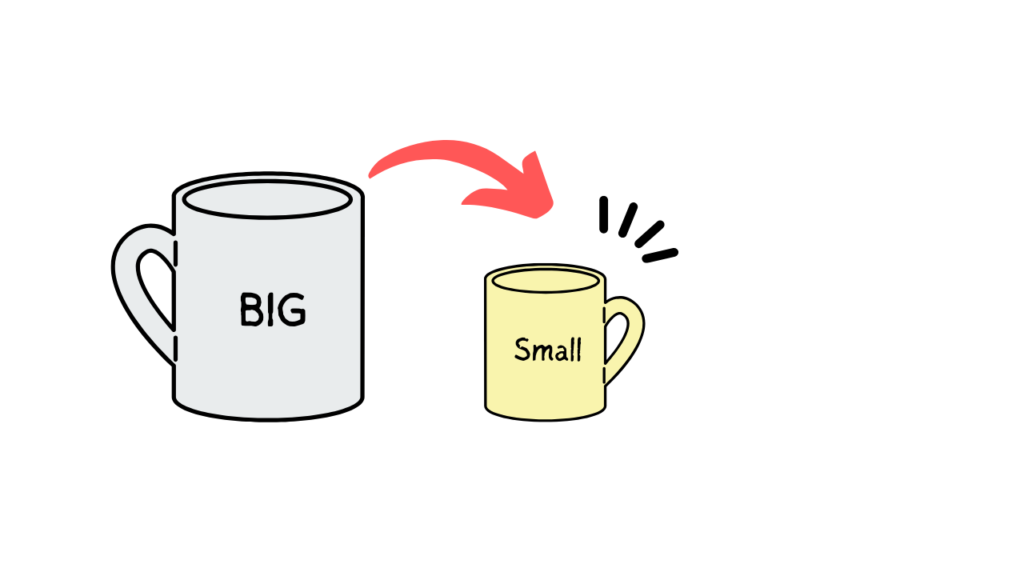
② 常温か温かいものを選ぶ
冷えは血流を悪くしたり、胃腸の働きを低下させてしまいます。まだまだ朝晩は寒いので、温かいものを取り入れてお腹から温めましょう。
③ 飲んだら出す・出したら飲む
飲んだら出す、汗やトイレなどで水分が出ていったら補給するという「循環させること」が重要です。特に汗をかくことを意識しましましょう。寒い時期は汗をあまりかかないので、軽い運動や入浴などで意識して出すようにすると、体に溜まった不要なものも排出されてスッキリ♪ 子供やお年寄りの方は喉の渇きに気づきにくいので、飲むタイミングを決めて水分不足を防ぎましょう。
欧米食などと比べ、和食はご飯や味噌汁、豆腐など比較的水分が多い食事です。そのため、1日3食きちんと食事をとっていれば、1日に必要とされる水分の約半分を食事からとっているといわれています。
もちろん体格や運動量、トイレの回数、生活環境(汗をたくさんかくなど)、疾患などによって、その人に必要な水分の量は異なります。そのため一概に2L必要というわけではなく、ご自身にあった量を補給することが大切です。たくさん飲むとなんとなく調子が悪い気がするという方は、無理にたくさん飲む必要はないかと思います。特に心疾患や腎臓機能が低下している方はご注意ください。
ご自身にあった水分量や補給の方法を知りたいという方は、管理栄養士まで気軽にご相談くださいね。